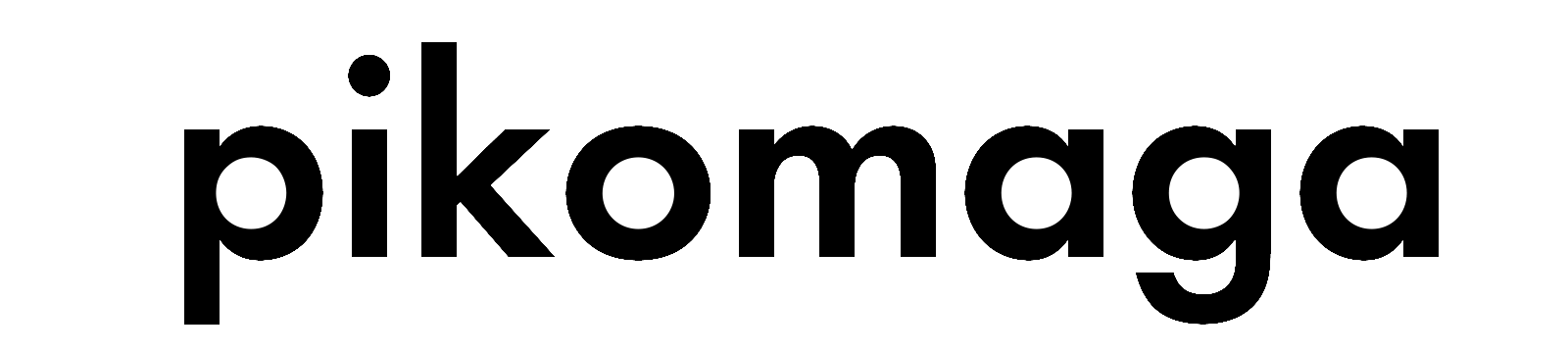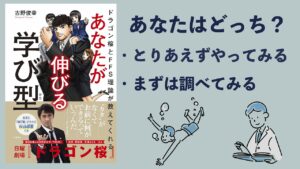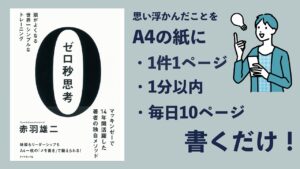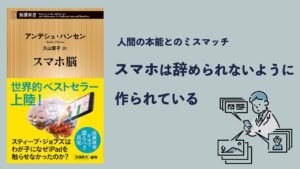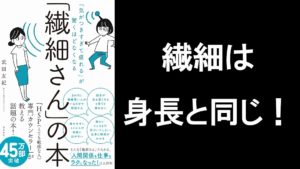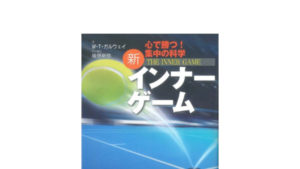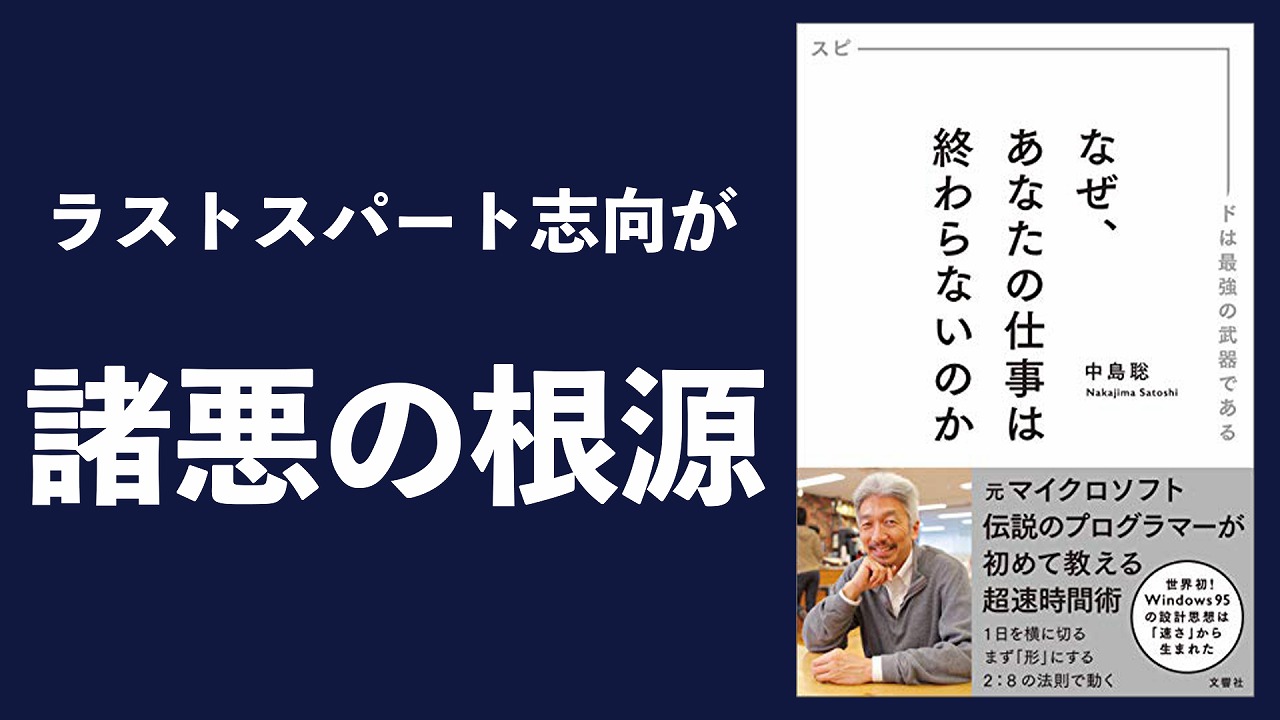
真面目に仕事をしているにもかかわらず、期限までに仕事が終わらず先送りなってしまう。
しかし、新しい仕事は待ってくれません。
新しい仕事もやらないといけないし、終わっていない前の仕事もやらないといけないので常に仕事に追われている状態から抜け出せません。
そんな状況で出会ったのが、「なぜ、あなたの仕事は終わらないのか?」という本です。
仕事が締め切りまでに終わらないのは、締め切り間際に頑張ろうとするラストスパート思考が原因。
その対策として全体の2割の時間で8割完成を目指す「ロケットスタート時間術」が紹介されています。
ラストスパート思考が諸悪の根源

この本の中では、ギリギリになるまで本気で仕事をしないラストスパート志向が仕事が終わらない根本的な原因と書かれています。
自分もこのラストスパート志向でした。
週末の金曜日に「この仕事、一週間でお願い」と上司から新しい仕事を任せられた場合
(金曜日)
一週間あればこの仕事は終わりそうだから土日はゆっくりして月曜から頑張ろう。
(月曜日)
まだ余裕があるし新規の仕事をどう終わらすかスケジュールだけ考えて、他の長期的な仕事をちょっと進めよう。
(火曜日)
今日は新規の仕事に手をつけた。
スケジュール通りには進んでいないけれど締め切りまでまだまだ余裕があるし今日はこれぐらい。
(水曜日)
このままでは締め切りの金曜日までに仕事が終わらない。
ほかの仕事は置いておいて、この仕事を重点的に取り組もう。
(木曜日)
他の仕事のトラブルや緊急の打ち合わせが入って時間が取れなかった。
徹夜で頑張らないと。
(締め切りの金曜日)
前日から徹夜しても終わらなかった。
自分と同じように仕事のスケジュールを組んでいる人は多いのではないでしょうか。
なぜラストスパート志向はダメなのか
では、具体的にラストスパート志向のどこがいけないのでしょうか。
・やってみないと仕事の全体像を把握できない
・予定通りに仕事が進むとは限らない
・締め切り間際の仕事は効率が悪い
やってみないと仕事の全体像を把握できない

概要を聞いただけで一週間で終わりそうと判断した仕事。
本当に一週間で終わるのでしょうか。
実際に作業を進めていくと、
・思ったより時間がかかる
・想定外の作業もしなけらばいけない
など、当初の想定と違うことがほとんどではないでしょうか。
このように、実際に仕事をやってみることで全体像を把握することができます。
予定通りに仕事が進むとは限らない

急な打ち合わせや体調不良など予定通りに仕事が進むとは限りません。
しかし、仕事のスケジュールを組む時にはイレギュラーな事態に対応するための余裕が考慮されていないことが多いです。
締め切り間際の仕事は効率が大幅に低下する

・締め切りに間に合わないかも
・間に合わないと上司に怒られる
嫌なイメージが無意識に頭にちらつくので仕事に集中できません。
このように締め切り間際の仕事は効率が大幅に低下してしまいます。
ロケットスタート時間術

これまでの説明でラストスパート志向がダメな理由がわかったと思います。
ではどうすればいいのでしょうか。
この本の中では、時間に余裕があるときにこそ全力疾走で仕事をして、締め切りが近づいたら流す「ロケットスタート時間術」が紹介されています。
10日で終わらせるタスクがあれば、
期限の2割の2日間でプロトタイプ(8割完成)の作成を目指してプロジェクトの当初からロケットスタートをかける。
そして、残りの2割の仕事は8日間でゆっくり行うというものです。
ロケットスタート時間術のいいところ
では、この「ロケットスタート時間術」にはどんなメリットがあるのでしょうか。
・期限内に終わるかどうか判断できる
・まずは全体像を描く方が効率がいい
・終わりが見えてから質を高められる
・仕事のメリハリをつけれる
期限内に終わるかどうか判断できる

上司から、
「この仕事10日間でお願い」と依頼された時、
その上司は10日間で終わる仕事量なのか計算していない場合が大半です。
なので、自分で期限内に終わるかどうか判断する必要があります。
今回の場合であれば、10日間の2割(2日)でプロトタイプ(8割完成)を作ることができるかどうかで仕事が期限内に終わるかどうかの見通しがつきます。
もし全体の2割の時間でプロトタイプが完成しなければ期限内に終わる可能性が低いので、上司に期限を延長してもらえるように交渉するなど何かしらの対応する必要があります。
締め切り間際ではないので相談された上司も対応しやすいです。
まずは全体像を描く方が効率がいい

絵を描く時に、いきなり眉毛の一本一本をこだわって描いても、全体のバランスが悪くなったりして結局修正することが多いと思います。
仕事も同じで細かい所をこだわり過ぎるよりも、どうせやり直しになるのだから細かい所は置いておき、まずは全体像を描く方が効率がいいです。
プロトタイプ(8割完成)を目標にすることで全体像を描くことができます。
終わりが見えてから質を高める
どんなに頑張って100%のものができたと思ってもも、振り返ってみるとそれは100%ではなく90%や80%のものに見えてしまうことがほとんどです。
そもそも最初から100%の物を作ることは不可能です。
スマホアプリが延々とアップデートを繰り返しているように100点の仕事など存在しません。
質を高めることはもちろん大切ですが、問題なのは仕事が終わる見通しが立ってもいないのに質を高めるためにあれこれ工夫してしまうことです。
スピードと質はトレードオフ。
仕事の質を追求したらスピードが遅くなることを忘れてはいけません。
質を追求した結果、締め切りに間に合わないような仕事の仕方をしていては本末転倒です。
まずプロトタイプ(8割完成)を作り提出できるレベルまで質を高めて、締め切りまで時間があればより質を高めてもいいかもしれません。
仕事のメリハリをつけれる

全体の2割の時間で仕事の8割が終わったとすると、このペースで進めれば締め切りよりも早く終わる可能性が高いです。
しかし、永遠に全力で働き続けることは不可能です。
いつも全力を出していると100%の能力を発揮できなくなっていきます。
なので2割の時間で仕事の8割が終わったとしても、残り2割の仕事を8割の時間で余裕を持ってやることは大切です。
余裕があるからこそ、また全力疾走が出来るようになります。
まとめ
あなたの仕事が終わらない根本的な原因はギリギリになるまで本気で仕事をしないラストスパート志向です。
(ラストスパート志向がダメな理由)
・やってみないと仕事の全体像を把握できない
・急な打ち合わせ、体調不良など予定通りに仕事が進むとは限りらない
・締め切り間際の仕事は効率が大幅に低下する
そこでこの本では、時間に余裕があるときにこそ全力疾走で仕事をして、締め切りが近づいたら流す「ロケットスタート時間術」が紹介されています。
(ロケットスタート時間術)
10日でやるべきタスクであれば、期限の2割の2日間でプロトタイプ(8割完成)の作成を目指してプロジェクトの当初からロケットスタートをかける。
そして、残りの2割の仕事は8日間でゆっくり行うというものです。
ロケットスタート時間術のいいところ
・期限内に終わるかどうか見通しがつく
・まずは全体像を描く方が効率的
・終わりが見えてから質を高めれる
・仕事のメリハリをつけられる
ロケットスタート時間術を使っても、寝る間を惜しんで仕事をしなければならないこともあるし、つらい時が全く無いわけではありません。
しかし、正しい時間の使い方をマスターすることで自分の能力を最大限発揮できるようになります。
ひょっとしたら、2倍以上の能力差がある人にも時間の使い方次第で勝てかもしれません。
真面目に仕事をしているけれど期限までに終わらずによく先送りになる人や、
計画を立てても計画通りにいかない事が多い人は、
「なぜ、あなたの仕事は終わらないのか?」を読んでみると解決の糸口がつかめるかもしれません。
また、本の中では著者の中島聡さんがビルゲイツと仕事をしたエピソードなど参考になる事が沢山書かれているので、もし興味があれば実際に本を読んでみてください。